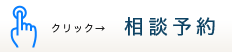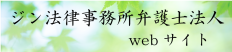裁判例:四肢麻痺の程度
大阪地裁平成31年1月30日判決
交通事故で麻痺の後遺障害が残ってしまう人もいます。
麻痺のなかでも、もっとも重い四肢麻痺状態の後遺障害では、その程度が争われるケースも少なくありません。
高度の麻痺状態なのか、中程度の麻痺状態なのかによって、等級が変わります。
事前認定での等級が必ずしも維持されるものではありません。
今回は、そのような裁判例の紹介です。
事案
原告X1が自動二輪車を運転。当時54歳。
被告Y1が自動車所有者。
被告Y2が普通乗用自動車の運転者。
二輪車と自動車が接触事故。
事故の発生は、平成23年2月13日午後3時2分頃。
道路は、南西方向(和歌山県新宮市方面)から北東(三重県熊野市方面)に向かって伸びる片側一車線の道路でした。
被告Y2は、被告車を運転して、本件道路を和歌山県新宮市方面から三重県熊野市方面に向かい進行。
原告X1は、原告車を運転して、被告車の左後方の本件道路上を同方向に向かい進行。
被告Y2が進行方向左側の路外施設である駐車場(以下「本件駐車場」という。)に被告車を左折進行させた際、被告車左前部と原告車右側面とが衝突し、原告X1は、原告車とともに路上に転倒したという事故態様でした。
被告らの責任
被告Y2は、被告車を運転して左折するに際し、左折地点の30m手前で合図をした上で、左後方の車両の有無を確認して左折進行すべき自動車運転上の注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、被告車を原告車に衝突させたということで、過失があるとされています。
被告Y1は、被告車の所有者ですので、自賠法上の運行供用責任です。
被害状況
被害者は、本件事故により頸髄損傷及び肺挫傷等の傷害。
入院39日、転院後400日の入院。
その後も、通院期間1062日、実日数287日の通院が必要でした。
病院リハビリ科の医師は、本件事故後の症状について、平成27年3月23日症状固定と診断。四肢麻痺等の後遺障害が残る。
損害保険料率算出機構は、頸髄損傷による四肢麻痺等の症状につき、四肢が完全麻痺を呈しており、膀胱直腸障害も認められることから、これらの障害のために生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に他人の介護が必要なものと捉えられ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、自動車損害賠償保障法施行令別表第一1級1号に該当すると認定。
四肢麻痺の程度
被告らは、四肢麻痺の程度について争いました。
中程度の麻痺であり、2級との主張を展開。
原告は、麻痺を伴う脊髄損傷においては、・高度の四肢麻痺があるか、・中程度の四肢麻痺があり、要常時介護の状態であれば、1級1号に該当するところ、原告X1は、症状固定時においても寝返りができない、いわゆる寝たきりの状態であり、知覚も四肢体幹で鈍麻しており全身にしびれがあったと反論。
医師の書面でも「手指機能がないため、巧緻動作を要する日常生活動作全般に介助が必要である。歩行が不能のため、移動を必要とする日常生活動作全般に介助が必要である。労働能力はない」状態であると書かれているこtから、高度の四肢麻痺が存在すると主張。
また、仮に、原告X1の四肢麻痺の程度が中程度であったとしても、日常生活動作の状態に加え、現に原告X1が自宅において常に介護を受けて生活していることからすれば、要常時介護の状態にあると反論しました。
裁判所における後遺障害の認定
医師意見書の記載として、身体の状況として、右上肢の麻痺は重度、左上肢及び両下肢の麻痺は中程度であるとの記載、頸髄損傷による不全四肢麻痺残存しており、右上肢は実用性に乏しく、右上肢にて補助具を使い食事は可能である。起立は手すりを使い何とか可能であり、歩行は装具及びロフストランド杖にて平地レベルにて短距離は可能であるが、耐久性はなく、常に見守りが必要であるとの記載を指摘。
別の医師の診断書では、座る動作は、一人でうまくできる、立ち上がる動作は、支持があればできるがやや不自由であるとの記載がある点を指摘。
また、つまむ動作(左)、握る動作(左)、さじで食事をする動作(左)、顔に手のひらをつける動作(左)、かぶりシャツの着脱、ワイシャツを着てボタンを留める動作、ズボンの着脱は、一人でできるがやや不自由な状態、つまむ動作(右)、握る動作(右)、タオルを絞る動作、紐を結ぶ動作、ズボンの前のところに手をやる動作(左)、尻のところに手をやる動作(左)、深くお辞儀をする動作及び屋内で歩く動作は、一人でできるが非常に不自由な状態であると記載されている点を指摘。
後遺障害診断書に添付された「日常生活動作検査表」において、
つまむ動作(左右)、握る動作(左右)、タオルを絞る動作、紐を結ぶ動作、さじで食事をする動作(左右)、顔に手のひらをつける動作(左右)、ズボンの前のところに手をやる動作(左右)、尻のところに手をやる動作(左右)、かぶりシャツの着脱、ワイシャツを着てボタンを留める動作、ズボンの着脱、靴下を履く動作、ボールペンなどで文字や絵を書く動作、片足で立つ動作、座った状態を維持する行為、屋内及び屋外で歩く動作、深くお辞儀をする動作、立ち上がる動作、階段を上る動作並びに階段を下りる動作につき、いずれも、一人では全くできない状態であると記載されている点も指摘。
そして、これらの書類に記載されている、日常生活動作について、ほぼ全てを行うことができないという評価について、以前及びそれ以後の時点における原告X1の日常生活動作の状態と齟齬がある上、本件後遺障害診断書に添付された「神経学的所見の推移について」と題する書面の記載内容とも相容れないものであり、上記「脊髄症状判定用」と題する書面及び「日常生活動作検査表」と題する書面の内容は、採用し難いとしました。
むしろ、これらに反するリハビリテーション総合実施計画書の記載は、リハビリテーションを現に担当した医療関係者において作成されたものである上、作成時点以後のリハビリテーションの内容等の決定の前提として、作成時点における原告X1の日常生活動作の評価を記載したものであると考えられ、同書面に記載されている原告X1の日常生活動作の評価に継続的に誤りが含まれるとは考え難いとし、こちらを重視するとの見解が示されました。
四肢麻痺の程度の認定
原告X1は、本件事故直後は、本件事故によって生じた頸髄損傷等により日常生活動作全般を行うことができず、その全てについて介助が必要な状態であったと認定。
しかしながら、その後のリハビリによって、その日常生活動作は改善していき、平成24年4月に退院する頃には、椅子での座位の保持、ベッドからの起き上がり動作、車椅子とベッド間の移乗といった基本的な運動動作や、食事、自己導尿による排尿等を自立して行えるようになっていたほか、同年9月時点においても、座る動作、立ち上がる動作、握る動作、つまむ動作等の基本的な運動動作、食事、更衣は、程度の差はあれ、一人で行える状態であったとも認定。
また、平成26年2月には、病棟トイレへの車椅子駆動、車椅子・ベッド間移乗、椅子座位保持及びベッドからの起き上がり動作といった基本的な運動動作、食事動作、排尿等を自立して行える状態であったと認定。
さらに、現在の原告X1の状態をみても、少なくとも、電動ベッドの操作や座位の保持、支持による立位保持及び自宅での車椅子での移動等の基本的な運動動作、食事、自己導尿による排尿等を行うことができている上、公的サービスの利用状況も、原告X2が不在の場合の自宅と病院との移動支援を受けているのみで、短時間であれば一人で過ごせることがうかがわれるとしています。
そうすると、原告X1の四肢麻痺の程度は、高度の麻痺の基準である、「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができない」(本件基発)程度のものとはいえず、中程度の麻痺の基準である、「障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの」(本件基発)の程度であると認められるとしました。
四肢麻痺と介護の程度
中程度という場合には、介護の程度が問題になってきます。
原告X2は、原告X1と同居して、同原告の介護をしているが、同居して介護を行っている者がいても、そのことから直ちに常時介護の状態にあると認められるものではないとしています。
そして、原告X1の日常生活動作については、常時介護の基準である、「食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの」に該当するということはできないと認定しています。
原告X1の後遺障害の程度は、「せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」(1級1号相当)とはいえず、「せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護を要するもの」(2級1号相当)というべきであるとしました。
この点に関し、損害保険料率算出機構による等級認定は、本件後遺障害診断書を基礎として、原告X1の四肢が完全麻痺を呈していることを前提としてなされているところ、本件後遺障害診断書の基礎となっている「脊髄症状判定用」と題する書面及び「日常生活動作検査表」と題する書面が採用できないことは上記のとおりであるから、本件後遺障害診断書も採用することができず、上記等級認定は、上記エの判断を左右するものではないとして、異なる結論を導き出しました。
損害の認定
このような後遺障害認定を前提に、損害が算出されました。
治療費 635万5010円
入院雑費 65万7000円
入院438日につき、日額1500円が相当である。
通院交通費 8500円
入通院付添費・在宅介護費 1032万6000円
将来の治療費・通院付添費 0円
原告X1が症状固定後も継続的にC病院に通院していることはうかがわれるものの、その治療の必要性や今後の見通し、治療費の額などについて何ら立証がないとし、仮に治療の必要性が認められるとしても、原告X1の症状固定後の通院に対する付添いに関する費用は、将来介護費に含まれるものと評価すべきであるとして否定。
将来介護費 3643万6052円
現在、原告X1の在宅介護を担っている原告X2は、上記症状固定時59歳であるから、以後8年間(対応するライプニッツ係数は6.4632。同時点で67歳。)は、同原告による介護が期待でき、その介護費としては日額6000円が相当であるが、その後の17年(対応するライプニッツ係数は7.6307〔=14.0939-6.4632〕)は、職業介護人による介護を要し、その介護費としては日額8000円が相当である。そうすると、原告X1の将来介護費用は、3643万6052円(=6000円×365日×6.4632+8000円×365日×7.6307)となる。
装具費 58万2621円
家屋改造費 475万1030円
休業損害 922万6739円
後遺障害逸失利益 1991万2694円
入通院慰謝料 500万円
後遺障害慰謝料 2400万円
小計 1億1725万5646円
過失相殺(15%)後の金額 9966万7299円(円未満切捨て)
さらに、本件事故前からの既往症として、第2・第3頸椎椎体の先天的な癒合に加え、第3・第4頸椎及び第5・第6頸椎の椎間部の脊柱管の狭窄が存在していたものと認められるとし、原告X1に生じた脊髄損傷は、転倒時における頸椎の過度の屈伸や旋回による圧迫等によって生じたものと考えられ、原告X1の第3・第4頸椎の椎間部の脊柱管狭窄が、同高位の頸髄損傷の発生及び拡大に一定程度寄与したと認めるのが相当であるとしました。
そこから、10パーセントの割合による素因減額。8970万0569円(円未満切捨て)。
既払い金として控除されたもの。
障害基礎年金 -592万8982円
被告らの任意保険 -1391万1951円(争いなし)
四肢麻痺状態の後遺障害で、事前認定で1級とされても、その後のリハビリ状況等が重視されることになり、必ずしも、その等級が維持されるわけではありません。
裁判では、あらためて主張立証が必要です。
交通事故のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。