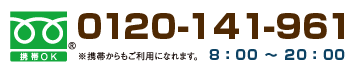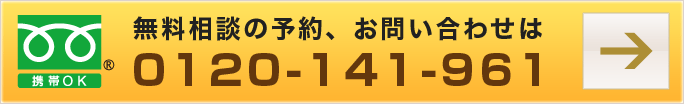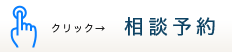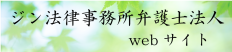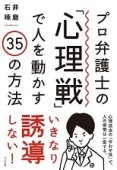損 害
逸失利益(死亡)
死亡事故の場合、労働能力を100%失ったものとし、将来得られたであろう収入を失ったとして、その利益分を損害として請求することができます。
死亡事故の逸失利益は、
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数
で計算します。
原則として、事故当時に得ていた収入が基礎収入となります。ただし、将来、実際に得ていた収入を上回るという立証ができれば、その金額が基礎収入となります。被害者の年齢が若い場合には、一般的に事故当時より収入が増えるだろうという見込みがあるため、平均賃金で算出することもあります。
若年者の基礎収入
平均賃金で算出することが多いです。
女子の逸失利益については、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するようになってきています。
生活費控除率
後遺障害とは異なり、死亡事故の場合、被害者本人の逸失利益を算定する際に、被害者が生きていれば必要だった生活費が不要になるため、一定額を控除することになります。
どの程度の金額を控除する化は、被害者の生活状況によって変わります。
被害者が一家の支柱で、被扶養者が1人の場合には40%、2人以上の場合には30%前後で決められることが多いです。
また、女性(主婦、独身、幼児の場合も含む)の場合には30%前後、男性(独身、幼児の場合を含む)の場合には50%前後とされることが多いです。
さらに、年金収入の場合には、生活費控除率を通常より高くする例も多いです。年金に占める生活費の割合が高いだろうという前提です。
就労可能年数
被害者が18歳以上の場合には、就労可能年数は、死亡から満67歳までとされることが多いです。67歳まで収入を得られる前提です。
高齢の方の場合には、67歳までではなく、異なる方法で算出することになります。
ライプニッツ係数
逸失利益は、本来、将来にわたって得られる収入です。それを、現時点で一括して支払ってもらうため、将来の利息分を差し引く計算をおこないます。現在は、就労可能年数に相当する年5%分のライプニッツ係数を用いるのが通常です。
例えば、就労可能年数が10年の場合、ライプニッツ係数は7.7217とされています。
10年間の場合、基礎収入の10年分が損害として認められるのではなく、基礎収入に7.7217を乗した金額が損害になります。
年金と逸失利益
被害者が遺族厚生年金を受給していた場合、これが逸失利益を算出する場合の基礎収入になるかというと、判例は否定しています(最判平成12年11月14日)。遺族厚生年金は、その遺族個人のためのものであるためであるというのが理由です。
老齢年金・障害年金については、遺族の生活を保障するという意味もあるため、逸失利益性を認めるのが裁判例の流れです。