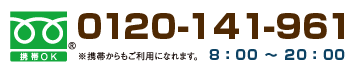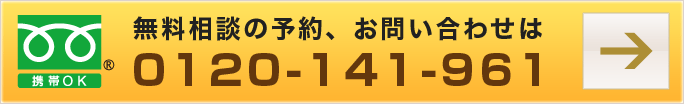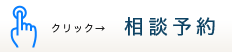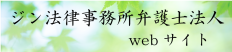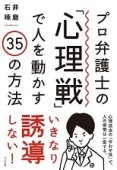後遺症の内容
鼻の後遺障害
交通事故で鼻に後遺障害を負った場合について説明します。
鼻の後遺障害で多いのは、嗅覚障害です。
においがわからなくなってしまう障害ですね。
これも、鼻の部位によって、分類されます。
慢性副鼻腔炎のように、呼吸性嗅覚障害の場合と、嗅神経の断裂等による末梢神経性嗅覚障害等の神経性嗅覚障害です。
神経性嗅覚障害には、頭部外傷、脳挫傷等が原因で嗅球から中枢側で障害が起きる中枢神経性嗅覚障害もあります。
嗅覚障害については、事故直後に発覚することは少なく、外傷の治療が落ち着いてから気づき、通院が始まることが多いです。
鼻の障害と等級表
鼻の後遺障害が自賠責の等級表ではどうなっているかの話です。
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
とされています。
欠損とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損することをいいます。
機能に著しい障害は、鼻呼吸が困難になったり、嗅覚を脱失することをいいます。
欠損状態によっては、外貌醜状の方が高い等級になることも多いです。
外貌醜状の場合、それぞれの等級での併合ではなく、いずれか高い方の等級で認知します。
鼻に欠損がない場合の後遺障害
欠損がない場合の障害については、直接の等級はなく、
神経障害に準じて12級、14級相当の認定を検討することになります。
たとえば、鼻の欠損を伴わない場合でも、
鼻呼吸困難の障害を残す場合には、12級相当、
T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力喪失値が5.6以上の場合には12級相当、
2.6以上5.6未満の場合には14級相当とされます。
鼻の後遺障害で認められる損害
治療費
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
休業損害
後遺障害逸失利益
など
鼻の後遺障害で争点になりやすいポイント
争点:後遺障害の存在
T&Tオルファクトメーターやアリナミンテストによる嗅覚状態の検査結果で立証していくことになります。
検査結果が基準をクリアしているかが問題になります。
争点:因果関係
嗅覚障害については、事故直後に気づきにくいという点もあり、事故との因果関係が争われやすくなります。
時間が経てば経つほど、事故と関係ないのでは?と反論されます。
過去に外傷があるような場合には、その際の治療や検査状況を確認しておき、事故以外の発生原因がないことを主張していくことになるでしょう。
争点:逸失利益
鼻の後遺障害の場合、後遺障害が認定されたとして、等級表どおりの労働能力喪失率が認められるかどうかが争われます。
もちろん、業務上、嗅覚を使う仕事であれば認定されやすいですが、それ以外の仕事の場合、等級表どおりの認定はされにくく、低い労働能力喪失率での算定や、慰謝料で考慮されるにとどまることも多いです。
嗅覚障害により、どのような不利益が生じているのか、具体的に主張・立証していくことが求められます。