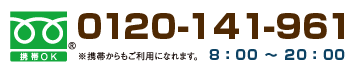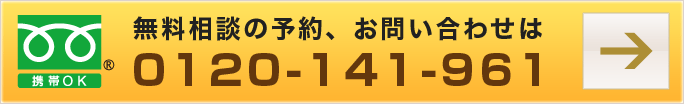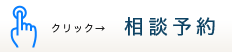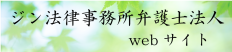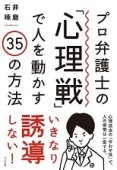後遺症の内容
耳の後遺障害
交通事故の後遺障害により、耳の問題では、難聴や耳鳴りが生じることがあります。
耳鳴りについては、頸椎の歪みが原因で生じるものもあります。
耳の障害
自賠責では、耳の聴力障害、耳介の欠損障害について等級表で定めています。
たとえば
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
というように両耳か片耳か、またその聴力の程度によって区分されています。
聴力を全く失ったとは、平均純音聴力レベルが90dB以上、または80dB以上で、かつ、最高明瞭度が30%以下のものとされます。
聴力を失った点に関する認定基準としては、それぞれの耳の平均純音聴力レベルの数値、両耳の聴力レベルと最高明瞭度との組み合わせで検討することになります。
また、欠損については、1耳の耳殻の大部分を欠損したものが12級4号にされています。
「大部分」とは、耳介軟骨部の2分の1以上をいいます。
両耳の場合には、1耳ごとに等級を定めて併合する扱いとなります。
両耳とも耳介部分の2分の1以上を欠損した場合には、併合で11級が認定されることになります。
ただ、この点を醜状障害で捉えると7級12号に該当する可能性があります。
2分の1以上にはならない欠損の場合も、外貌醜状での認定を検討することになります。
耳鳴りについては、検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものについて12級、常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるものについて14級を準用するとされています。
耳の後遺障害の検査方法
聴力については、純音による聴力レベルの測定結果、語音による聴力検査結果をもとに認定されます。
純音による聴力の検査としては、純音聴力検査が使われます。
オージオメータを使った検査で、単一周波数の純音を使い、周波数や強さ、長さの聞こえ方を分析する検査方法です。
ヘッドホンからの音をきく検査です。
日をかえて3回検査されます。各検査は7日程度の間をあけてすべきとされています。
1回の検査に30~40分。
後遺障害の認定については、2回め、3回めの平均純音聴力レベルの平均で認定されます。
語音による聴力の検査としては、スピーチオージオメーターにより語音聴力検査が使われます。
日常的に使う語音を検査音として使い、聞こえ方を検査する方法です。
これらの検査以外に、ABR、SRと呼ばれる他覚的聴力検査を求められることもあります。
ABRは聴性脳幹反応、SRはあぶみ骨筋反射です。
これらは、被害者の意思で検査結果が変わらないとされるため、保険会社が求めてくることがあります。
耳鳴について
耳鳴については、耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては12級相当、難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるものについて14級相当とされます。
いずれも30dB以上の難聴を伴うことが必要とされます。
耳鳴に関する検査とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいうとされます。
検査結果のオージオグラムを後遺障害診断書に添付します。
耳の後遺障害で認められる損害
治療費
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
休業損害
後遺障害逸失利益
など
耳の後遺障害で争点になりやすいポイント
争点:・後遺障害の存在や程度
聴力の障害については、認定基準が明確ですので、これを満たすのであれば、そのような記載がされた後遺障害診断書を作ってもらう必要があります。
争点:因果関係
診療記録等から、事故直後からの難聴や耳鳴りを訴えていたことが分かる場合には、争われにくいですが、事故から一定期間経過後に症状が出ているような場合には、争われやすくなります。
耳鳴り等が気になった場合には、はやめに耳鼻科を受診しておくようにしましょう。
争点:逸失利益
耳の後遺障害の場合、後遺障害の認定がされても、逸失利益を決める際の労働能力喪失率が、等級表のとおり認められないこともあります。
後遺障害によって、仕事や日常生活にどのような影響が出ているのか詳しく主張立証する必要があるでしょう。