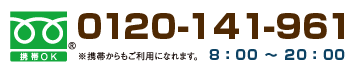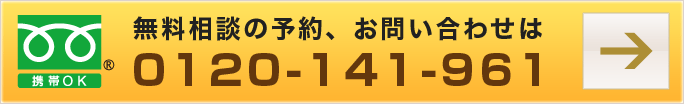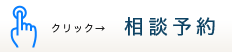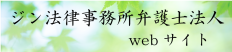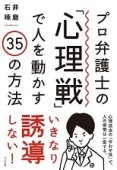後遺症の内容
眼の後遺障害
交通事故で眼に後遺障害が残ってしまうことがあります。
自賠責等級では、眼の後遺障害について、眼球の障害と、まぶたの障害に分けられています。
眼球障害は、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の4つに分かれています。
まぶたの障害は、欠損と運動障害の2つに分かれています。
眼球の障害
視力障害として1級~13級
例)両眼が失明 1級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級1号
1眼の視力が0.6以下になったもの 13級1号
調節機能障害として11級、12級
例)両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 11級1号
運動障害として10~13級
例)正面を見た場合に複視の症状を残すもの 10級2号
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 12級1号
視野障害として9級、13級
例)両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 9級3号
等級表での「視力」は矯正視力をいいますので、裸眼ではなく、メガネ、コンタクトレンズによって得られた視力が含まれます。
「失明」は眼球を失ったものや、明暗を区別できないもの、ようやく明暗を区別できる程度の状態をいいます。
眼球破裂をしてしまったような場合には、眼球摘出をすることが多く、失明と認定されます。
「 眼球に著しい調節機能障害」とは、調節力が2分の1以下に減ったものをいいます。
「 眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、ヘスコオルジメーターで眼球の注視野の広さが2分の1以下に減ったものをいいます。
眼球を動かす筋肉は6種類あり、それらの筋肉は3つの神経に支配されています。
この神経に異常が生じることで、筋肉を動かせなくなるのです。
注視野は、頭部を固定して、眼球の運動だけで見える範囲です。
複視は、ものが二重に見える状態です。
眼筋の麻痺等によって、左右の眼の網膜の対応点にずれが生じることなどが原因とされます。
半盲症とは、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいいます。
視野狭窄は、視野周辺の狭窄が起きることで、周囲を確認できなくなるため、歩行等の動作が困難になります。
まぶたの障害
欠損障害として9~14級
例)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 9級4号
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 14級1号
運動障害として11,12級
例)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 11級2号
「 まぶたに著しい欠損」は、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
「 まぶたの一部に欠損を残し」は、まぶたを閉じたときに、角膜は覆うことができるものの、球結膜(しろめ)が露出している程度の状態です。
「 まぶたに著しい運動障害」は、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆えない場合や、まぶたを開いたときに、瞳孔を覆う状態をいいます。
まぶたの欠損は、外貌醜状と評価することもできます。この場合、いずれか上位の等級を認定します。
眼の後遺障害と併合繰り上げ
両眼の視力障害については、障害等級表に記載されている両眼の視力障害の該当等級で認定するため、1眼ごとに等級を定めて、併合繰り上げという扱いはされません。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位の場合には、その1眼のみに障害が存するものとみなして認定されます。
同一の眼球に、系列が違う後遺障害が2以上残ってしまった場合は、併合の方法を用いて、相当等級を定めるとされています。
まぶたの欠損の場合、外貌の醜状障害としても考えられるので、そちらの観点からも検討し、いずれか上位の等級が認定されることになります。
眼の後遺障害で認められる損害
治療費
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
休業損害
後遺障害逸失利益
など
眼の後遺障害で争点になりやすいポイント
争点:後遺障害の有無
等級表に該当する後遺障害が残っていること自体が争われることが多いです。
交通事故の外傷によって、どのような症状が残っているのか特定し、立証する必要があります。
各種の症状により検査内容は異なってくるので、有益な検査をしたうえで、検査結果や所見について医師に診断書等を作成してもらうことになります。
眼球の器質的損傷にういては眼底検査等により、視神経損傷については、VEP検査、ERG検査等により判断されます。
ERG検査は、網膜に光の刺激を与えた際の、網膜の活動電位をグラフに記録したものです。虚偽の申告ができないことから、この検査結果が重視されることも多いです。
争点:因果関係
眼の障害について、等級表に該当するような後遺障害が認められたとして、それが交通事故を原因とするものかが争われることも多いです。
特に、事故から一定期間が過ぎた後に発症したような場合、因果関係が否定されやすくなります。
視力障害の原因を、主張・立証して特定していく必要があります。
争点:逸失利益
眼の障害については、仕事の職種により、等級表以上の労働能力喪失率が認められるケースもあります。
眼を使う仕事は多く、視力の低下、喪失により大幅に労働能力が喪失することはあるでしょう。
実際の仕事の業務内容や、後遺障害による影響を具体的に主張・立証していくことが有効です。