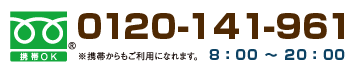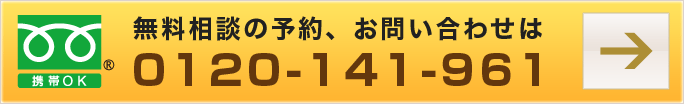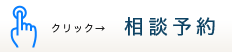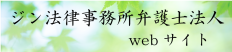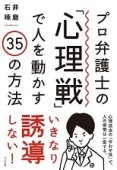後遺症の内容
遷延性意識障害
交通事故で頭部に衝撃を受けた場合、遷延性意識障害の後遺障害を負ってしまうことがあります。
遷延とは長引くという意味です。
意識障害が長引くものですので、昏睡状態や外部からの刺激に反応しない状態が続きます。
いわゆる植物状態が続いているともいえます。
脳死状態とは異なり、脳幹機能はほぼ正常に保たれている、自発呼吸はあることが特徴です。
遷延性意識障害の介護
このような遷延性意識障害の場合、患者の自己治癒力にかけて、現状維持を図るため、常時介護が必要とされます。
床ずれ防止のために体位をかえたり、排泄の処理、入浴、マッサージ、淡の吸引等の介護が必要とされ、負担が大きいものとなります。
通常の病院に入院している場合、積極的な治療ができないことから、入院期間が3ヶ月程度を過ぎると退院や転院を促されることも多いです。
家族としては受入先を探すことになります。
遷延性意識障害の後遺障害
交通事故の後遺障害としては、「神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する」ものとなりますので、自動車損害賠償保障法施行令別表第1の1級に該当するもので、労働能力喪失率は100%とされます。
常時介護が必要となることから、自宅介護をする場合、他の後遺症による損害賠償請求で問題となる逸失利益や後遺障害慰謝料等の損害のほか、
自宅・自動車改造費
将来介護費による職業介護人費用
将来雑費
介護家族固有の慰謝料
が争点になることが多いです。
遷延性意識障害と定期金賠償
特に、遷延性意識障害については、被害者の余命が平均余命より短いというデータがあることから、加害者側から、まとめて支払う一時金の賠償ではなく、一定期間ごとに支払う定期金賠償方式によるべきと主張されることが多いです。
また、遷延性意識障害の場合、いわゆる植物状態であるとして、日常の生活費はかからないという話を前提にして、生活費控除を行うよう主張されることもあります。
職業介護人費用
遷延性意識障害では、介護の負担が大きいことから、親族のみでこれをおこなうには限界があり、職業介護人を雇う必要があるでしょう。
この費用が認められるか、認められるとして人数や期間などが争点となりやすいです。
将来の介護費用を一時金でもらう場合には、基準額に対して、余命までの期間に対するライプニッツ係数をかけた金額が損害となります。
自宅・自動車改造費
施設入所での介護ではなく、自宅での介護となる場合、自宅の居室、玄関、廊下、浴室等を改造したり、介護リフトやエレベーターを設置したりすることがあります。
交通事故訴訟の中では、自宅改造費について、負担した全額が認められるというものでもなく、被害者の介護に必要かつ相当である場合に損害賠償の範囲に含まれ、同居親族がその使用や改造で利益を得ている場合には、一定の減額がされることがあります。
改造にとどまらず、建替えやバリアフリーのマンション購入費用の一部が認められることもあります。
自動車の改造費についても、必要かつ相当の範囲であることは家の改造費と同じですが、車には耐用年数があり、一定期間ごとに買い替えが必要になるので、その計算が必要になります。
将来雑費
介護には、いろいろと必要な物品があります。
介護用品として、介護ベッド、リフト、痰吸引器、血圧計等の医療機器が必要となりますし、消耗品として、紙おむつ、尿とりパッド等を定期的に購入することになります。
これらの介護器具、介護用品については、平均余命までの購入費用が損害に含まれます。
ただ、耐用年数がある器具については、自動車と同じく一定期間ごとに買い替えが必要になるとして、計算されることが多いです。
成年後見人費用
遷延性意識障害の場合、被害者本人に意識がないことから、成年後見人を選任したうえで、加害者側の保険会社と交渉等をしていくことになります。